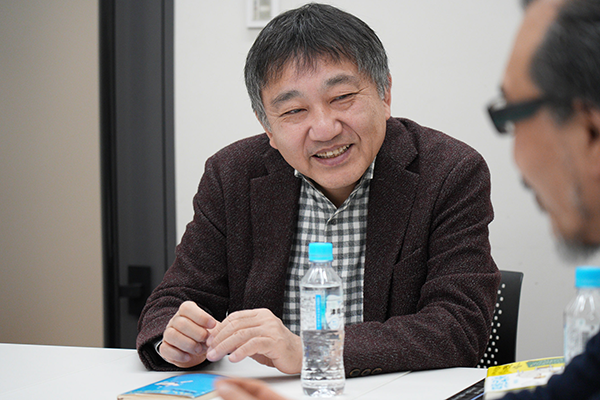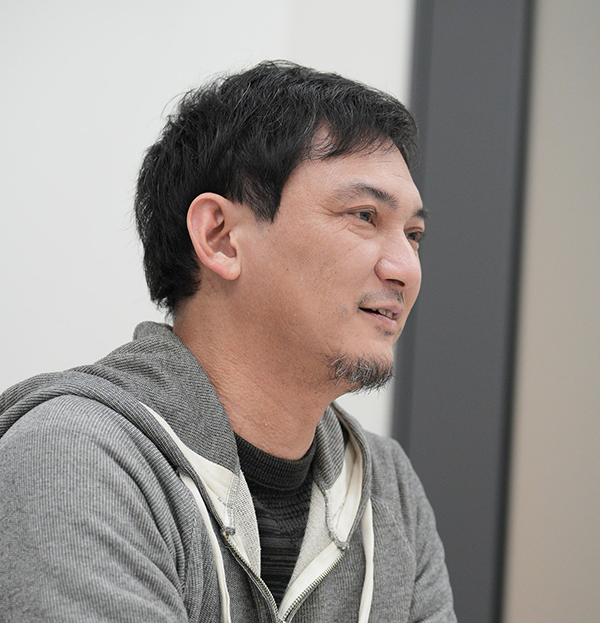どうにも本が売れません(back2)
「どうにも本が売れません」
出版人のための悩み相談室
(Back Number)
回答者
髙橋秀実
石原壮一郎
渡辺謙作(スペシャルゲスト)
気鋭のノンフィクション作家・髙橋秀実氏と抱腹絶倒コラムニスト・石原壮一郎氏が、出版人のあらゆる悩みに回答します。
と思いましたが、今回は脚本家・映画監督の渡辺謙作氏を迎えて、あるひとつのテーマについて熱く語り合っていただく特別編です。ちなみに映画『はい、泳げません』は、渡辺氏の脚本、監督作品。
今話題のドラマ『アンチヒーロー』(TBS系)主演の長谷川博己さんが髙橋さんを演じられている名作秘話もうかがいましょう!

髙橋秀実(たかはし・ひでみね)
ノンフィクション作家
1961年神奈川県横浜市生まれ。東京外国語大学モンゴル語学科卒。テレビ番組制作会社を経て、ノンフィクション作家に。『ご先祖様はどちら様』で第10回小林秀雄賞、『「弱くても勝てます」 開成高校野球部のセオリー』で第23回ミズノスポーツライター賞優秀賞を受賞。他の著書に『TOKYO外国人裁判』『ゴングまであと30秒』『素晴らしきラジオ体操』『からくり民主主義』『はい、泳げません』『趣味は何ですか?』『おすもうさん』『男は邪魔!』『損したくないニッポン人』『不明解日本語辞典』『やせれば美人』『人生はマナーでできている』『定年入門』『悩む人』『道徳教室』『おやじはニーチェ 認知症の父と過ごした436日』ほか。

石原壮一郎(いしはら・そういちろう)
コラムニスト
1963年三重県松阪市生まれ。月刊誌の編集者を経て、1993年に『大人養成講座』でデビュー。その後、念入りに「大人」をテーマにした本を出し続ける。大人歴10年を超えたあたりで開き直って出した『大人力検定』は、それなりにヒット。その後、検定をテーマにした本をあきれるぐらい出し続けるが、どれも今ひとつ。昨今は「コミュニケーション力」に活路を見出そうとしている。最新作は『押してはいけない 妻のスイッチ』。そのほか、故郷の名物を応援する「伊勢うどん大使」「松阪市ブランド大使」を務める。

渡辺謙作(わたなべ・けんさく)
映画監督・脚本家
1971年福島県生まれ。『プープーの物語』(98)で監督・脚本デビュー。そのほかの監督作に『フレフレ少女』(08)、『エミアビのはじまりのはじまり』(16/脚本兼任)、『はい、泳げません』(22/脚本兼任)ほか。脚本を担当した『舟を編む』(13)で第37回日本アカデミー賞最優秀脚本賞を受賞。主演とプロデューサーを兼ねた『波』(01)は第31回ロッテルダム国際映画祭でNETPAC賞を受賞。そのほか、脚本家としてWOWOW『石の繭 殺人分析班』(15)ほか。
撮影 落合星文
相談03 (35歳・書籍編集者) 第1回 今回はこれまでとは違います ——今回の質問のテーマは「原作と脚本」です。髙橋秀実さん原作の映画『はい、泳げません』の脚本、監督をされた渡辺謙作さんをゲストに招き、原作と脚本について、それはそれは鋭く深く話し合う予定です。よろしくお願いします。 髙橋 これまで、この連載では「本が売れません、困った」みたいな埒の明かない話ばかりしてきましたが、今回は違います。テーマがあります。「原作と脚本」です。 石原 杞憂かもしれませんが、わざわざ危ない橋を渡ろうとはしていないでしょうか。 ——杞憂です。しかも、ゲストも来ていただきました。映画監督、脚本家の渡辺謙作さんです。 渡辺 よろしくお願いします。 一同 よろしくお願いします。 ——本を売るには映像化、テレビドラマ化とか映画化という手段がありますよね。 髙橋 そこです。私の作品をどなたかが映像化してくれるときには、そこに売れるためのヒントがあるような気がします。私は「これがいい」と思って本を世に出すだけですが、テレビドラマのつくり手などは公共の電波を使って、全国民に向かって作品を出すので、本人の思い込みだけでは済まされない。ひとりよがりは許されない。多くの人々にウケなくてはいけない。大衆の琴線を打ちふるわせなければいけないという使命を帯びるわけですから、そこには「こうすればヒットする」というヒントが必ずあるはずです。 石原 うらやましい。爪のアカを煎じて飲みたいところです。 髙橋 私の例でいうと『「弱くても勝てます」開成高校野球部のセオリー』(新潮文庫)という作品があります。 渡辺 読みました。おもしろい作品でした。 髙橋 原作では、甲子園を目指しているのは実は私だけなんです。野球部の生徒たちは「甲子園、べつに……」という感じでして。 渡辺 彼らが目指すのは、東大ですものね。 髙橋 甲子園より六大学で神宮球場に行きたいとか。私が保護者のみなさんに「甲子園に行くまで、取材させていただきます」とご挨拶したときなんか、大爆笑されました。 一同 (笑) 髙橋 ところが男子校の開成高校がドラマ化(*)されたときには男女共学となっていました。野球部にはマネージャーがいて、それが有村架純さん。 石原 野球部だけ、入りたい。 髙橋 ドラマでは、彼女が野球部員に「打って」と言う。 石原 たまりません。 髙橋 彼女に言われれば、そりゃあ誰だって打とうとするでしょ。原作のテーマは、どうやって部員たちのモチベーションを上げるか、ということだったんですが、有村さんの登場で、いきなり問題が解決しちゃう。試行錯誤を重ねていく原作が、ドラマでは彼女が「打って」と言うだけで解決しちゃったんです。 ——原作にそんな要素はありませんでした。 石原 そこで髙橋さんは、ご自分の作品『弱くても勝てます』に何が欠けているかがわかったんですね。
髙橋 有村架純さんが欠けていた。つまりは恋。恋がなければドラマは始まらないんです。そこで開成高校の校長(当時)に提案したんです。「女子を入れてください。そうすれば、生徒たちはがんばりますから」。 ——……。 髙橋「女子が入ることで男子はやる気になります。なんで女子を入れないんですか?」と校長にたずねました。すると校長は「うちはリーダーシップを育成するための学校なのです」。つまり、開成高校を出て東大に行き、官僚になったり、経済界など、さまざまな分野でトップとなる人材を育てる。エリートを養成する、トレーニングを積む場なんです。ところがそこに女子が入ると彼女たちにリーダーシップをとられてしまい、トレーニングにならないんだとか。逆に従う癖がついちゃったりなんかする。確かに有村架純さんが転校してきたら、勉強にも集中できないかもしれませんね。なんとなくわかる気はしますけど……。 石原 だけど、それではドラマにならない。 渡辺 それはドラマなどでは、よく行なわれています。脚本をつくる側も「入れたほうがいいですかね」みたいな話をします。 石原 映像をつくる人たちはドラマには「男女のほのぼのとした何かが必要」と考えているのでしょうか? 渡辺 というか、絵面ですね。時代劇なんて男ばっかりになるので、しょうもない役でも誰かの奥方をワンカット入れようとか。 石原
由美かおるがお風呂に入るところとか。 渡辺 ハハハハ。江戸時代は女性も出られるけど、戦国時代だと野郎ばかりです。だから「実は男装の女性でした」みたいなキャラが出てきたりとか。
石原 女子高生がタイムスリップしてきたりとか。 おっさんがプールでバタバタって ——あの。そろそろ本題に入りましょうか。 石原
では、脚本、監督をされた渡辺さんにうかがいます。髙橋さんの作品『はい、泳げません』のように、おっさんがプールでバタバタしている話を映画にしようと思ったのは、なぜなのでしょうか? 渡辺 僕も泳げないんですよ。 一同 (笑) ——いい話です。 渡辺 ただ、同じ泳げないにしても髙橋さんのように「水泳のレッスンに行こう」というガッツはまったくありませんでした。 ——でも、この作品を選びました。 渡辺 開成高校野球部の『弱くても勝てます』がおもしろかったので、本屋で横に並んでいた『はい、泳げません』もいいかなと手に取ったら、引き込まれました。 石原 読者の鑑ですね。 渡辺 この作品の主人公は髙橋さん自身で、すごく内省している。ノンフィクションでありながら私小説のようで、読んではまりやすかったところはあります。 石原 でも、この作品はひとりの中年男が少しずつ泳げるようになっていく話です。 髙橋 それだけ。だから何だ、という話ですよね。 渡辺 つまり、レッスンに行く動機が何もない(笑)。ということは、髙橋さんは仕事だからプールに行かれたのでしょうか? 髙橋 仕事ですね。取材というか。 一同 ……。 渡辺 映画の場合はそうはいきません。40年間泳げなかった人間が水泳のレッスンに通うようになることを考えると、大きな動機が必要になります。 石原 主人公がルポライターでは映画にならない。 渡辺 プロデューサーもO Kを出しません。 石原 主人公が離婚したとか、子どもがたいへんなことになったみたいな。 渡辺 そう、何かがないと始まりません。泳げないルポライターが仕事で水泳のレッスンに行く映画はありえません。 石原 今回は渡辺さんがプロデューサーに相談する段階で、現在の形ができたのですか? 渡辺 そうです。頭でっかち中年男が、女性コーチにしごかれる形です。 髙橋 それは原作通りです。現実の高橋桂コーチは、リーダーシップを備えた女性です。もともと彼女のレッスンはスゴいという評判から、その本をつくるという企画がスタートしました。それで、編集者からレッスンに参加するように言われまして。 石原 高橋桂コーチのすばらしさは、作品を読んでも伝わってきました。 髙橋 すばらしさは、当初わかりませんでした。だってレッスン初日に、彼女から「髙橋さん、泳げます?」と訊かれ、「泳げません」「じゃあ、100メートルいってください」。 一同 (笑) 髙橋 泳げないから、ふたかきして足を着きます。すると「なんで立つんですか?」「いや、泳げないんです。泳げないから来ているんです」「そんなはずはありません。泳げてます」。これが、彼女の指導方法なんです。 石原 すばらしいムチャぶりです。 髙橋 しかも他の生徒はすべて女性で、みんなが言います。「なんで立つの?」。 一同 (笑) 髙橋 レッスンではプールの2レーンをひたすら往復するので、私が立つと後の人たちが詰まってしまう。みなさん泳ぎに来ているのに、立つ人間がひとりいるだけで、かなり迷惑なわけです。「すみません」と謝るんですが、息継ぎも何もできないからすぐまた立つ。立ってまた「すみません」。しまいに企画発案の編集者に言いました。「申し訳ありませんが、書けません」。 ——「泳げません」の前に「書けません」ですか。 髙橋「書くのは無理です」と言ったんです。コーチが何を言っているのかよくわからないし、プールの中ではメモもとれませんから。すると編集者から「なんで?」と。 石原 生徒の次は編集者が詰めてきました。 髙橋 そこで私は「泳げないどころではなくて、水の中に入るのがこわいんです」と告白しました。いわば水恐怖症。「そもそも水に恐怖を感じるのはなぜか」ということを延々と釈明していたら、「じゃあ、それで1章分ができたわね」と言われました。 ——すばらしい。編集者の鑑です。 石原 つまりレッスンはやめられなかったんですね。 髙橋 季刊誌の連載だったので、〆切は3か月に1回。もともと行きたくないから、次の〆切の3日前でやっとレッスンに行くわけです。3、4日続けて通えば泳げるようになるかもしれないのに、行かないから全然泳げるようにならない。プールで立っては、みんなから「なんで立つの?」。しかも指導は「泳げているから、立ってはいけません」。 ——立板に水のようです。泣き言が。 髙橋 隣のコースにはハラダさんという男性コーチがいて「さあ~みなさん、今日はバタ足をやりましょう」と指導していました。バタ足とはこういうもので、じゃあビート板を使って泳いでみましょう、ああいいですね、素敵です、という感じです。私としてはそっちに行きたかった。 石原 たしかに水泳教室っぽいですね。 髙橋 そのレッスンなら、1章は「水がこわい」、2章は「バタ足」、3章は「息継ぎ」と進んで、最終的に「はい、泳げました」という構成が考えられる。 石原 でも読者は、髙橋さんが水泳のレッスンで苦しむ姿を楽しみたい。 髙橋 そうかもしれないけれど、隣のレッスンなら「今日はバタ足をマスターしたぞ」というような達成感がありそうでしょ。一個一個の技術を会得して、最終的に出来上がり。構成的にもまとまりがいい。 石原 でも、高橋コーチはそれはしなかった。 髙橋 しない。一個一個、分解しない。部分ではなく体全体で泳ぐ。だいたい、桂コーチはバタ足もしませんから。バタ足は、それこそバタバタするだけで、かえって泳ぎの邪魔なんです。 石原 本には「コーチの言うことがころころ変わる」とも書いてありました。 髙橋 そう。 ——「泳がないでくださいと言われた」とも書いてました。 髙橋 そう。 石原「コーチの言っていることが前回と違う」とも書いてました。 髙橋 そう。 石原 原稿にしたときにコーチから「私はこんなこと言ってない」とかはなかったんですか? 髙橋 なかったですね。ただ、最初にコーチが私に「泳げますか?」と聞いたとき、私が「泳げます」と答えた、と彼女は言うんです。 ——食い違いましたか。 髙橋 私は「はい、泳げません」と言ったんです。この「はい」は、質問に対する反応であって肯定ではありません。小学生が先生に「これ、わかる人?」と訊かれて、「はい」「はい」「はい」と挙手し、「じゃあ髙橋君、答えは?」と指名されて「わかりません」と答えるのと同じなのです。 石原「はい」ときたら、「泳げます」がくるものだとコーチは思われたんですね。 髙橋 いまだに、その言った言わないでもめています。 ——いけませんね。 髙橋「泳げないんだったら、いきなり100メートルではなく、他の方法があったのに」と。 石原 でも、最終的には25メートルを泳いだんですよね。 髙橋 泳ぎました。 石原 いまでも泳いでますか? 髙橋 いや、まったく。 一同 (爆笑) ——せっかく泳げるようになったのに、どうして泳がないんですか? 髙橋 こわいんです。水が。 ——……。なかなか話に入れません。「泳げないおじさんの話」はこれで終わります。では、次回は、いよいよ本題に入ります。 第2回 私、忖度されてますか 石原 作品が映画化されるときには、髙橋さんはまず何をしますか? 髙橋 本に登場する方々に連絡します。脚本も見せたりして、「これでいいでしょうか?」と許可をとります。 石原「こんな脚本はイヤです」と言われたら? 髙橋 もちろん、製作者に「これはやめてください」と話します。 ——髙橋さん自身は脚本を読んで「これは困るな」ということはなかったんですか? 髙橋 困るというか、この映画には、原作に登場しない妻が出てくるんです。 石原 それは、困ります(笑)。 髙橋 以前、NHKで『負けぬが勝ち』というテレビドラマが放映されました。『ゴングまであと30秒』(草思社)というボクシングジムのノンフィクションが原作だったんですが、そこにも妻が出てくる。 石原 本にはまったく出てこないのに。 髙橋 そうなんです。それで最初のシーンで主人公の私がパチンコをやっている。仕事もろくにせずにボクシングジムのトレーナーをしている。しかも赤いサンダルを履いている。 石原 奥さんのサンダルを突っかけてパチンコしている。 髙橋 ヒモであることを表現しているんでしょうが、ヘンでしょ。そもそも私の足のサイズは27・5センチで、妻は23センチですから、彼女のサンダルは入らない。 渡辺 昭和感を出したかったんでしょう。 髙橋 確かに私はなにもかもデタラメで、ヒモだったことも事実なんですが、それにしたって女性の描き方が旧態依然としてますよね。それで妻が赤いサンダルの部分に「古い」と赤字を入れまして。ここもおかしい、あそこもおかしいと脚本を真っ赤にして戻しました。彼女は描かれた当人でもありますが、映画にも詳しい敏腕編集者ですからね。これじゃまるで『TATTOO(刺青)あり』じゃないの? と。 ——あ、映画界を批判しますか。 渡辺 だけど映像業界には「主人公は男じゃないといかん」というプロデューサーは多いです。「ヒロイン映画はヒットしない」という考えがまだあります。ハリウッドもたぶんそうで、大作ほど主人公は男が多いですね。 髙橋 えっ、そうなんですか。 渡辺 女性が主役の脚本を僕が書いても「これは男にならないのか」と言われることはあります。「この作品は女だからいいんじゃないですか」と言っても、だいたい使ってもらえないです。 石原 脚本を書きあげて「やっぱりボツ」みたいなことはあるんですか? 渡辺 よくあります(笑)。 石原 たいへんですね。 渡辺 だけど、こっちとしても撮りたい。だからいろいろ言われても「わかりました」って書いちゃうわけです。そうすると、ますますつけあがって「これはダメ」「あれもダメ」とか。 石原「主人公を男にしろ」とか言われて。 渡辺 そう。 ——今回の髙橋さんの作品は、事前の打ち合わせをしたんですか? 渡辺 この作品は、まず脚本を書きました。 石原 強い思いで映像化したいと。 渡辺 そうですね。 石原 すばらしい。ちなみに髙橋さんは、映画で全然違う設定になってても不満はなかったんですか?
髙橋 それはないですね。だって、原作のまんまじゃ映画にはならないでしょ。 一同 (笑) 渡辺 作者の泳げないことを内省する屁理屈がおもしろかったので、生かすには「あ、哲学者」って思い浮かんで、主人公を哲学を教える大学教授にしました。 髙橋 脚本を見せてもらっても、私なんかは正直言って、よくわかりません。セリフだって実際に俳優がしゃべったらどうなるのか。NHKドラマのときも脚本を見て「こんな陳腐なセリフ、ありえない」と思ったんですが、倍賞美津子さんが言ったら、ものすごい説得力がありまして。同じセリフでも、本と脚本ではまったくの別物ですよね。 石原 すると、脚本では「ここを変えてほしい」はなかったんですか? 髙橋 それはあります。 石原 あ、あるんですね。 髙橋 それはやっぱり妻の描写です。 石原 ほう。奥様ですか。 髙橋 水泳部分はおおむね原作にそってくれていましたが、それ以外の私生活の部分。だって、いきなり離婚したりするんですよ。僕たちは離婚なんかしてないのに。 一同 (笑) 渡辺 奥さんと髙橋さんの意見はできるだけとり入れて「ちょっとここは変えられないんですけど」「それはこういう理由です」と、メールでやりとりをしました。 髙橋 けっこうしましたね。だけど、離婚はやめてくれ、とは言えなかった。 石原 離婚はイヤだって言ったら、話が成り立たない。 髙橋 渡辺さんが脚本を書いて監督までされている。つまり、よっぽど作品に思い入れがあるはずなので、そこに水を差しちゃいけないと、遠慮したんです。水中の話ですけど(笑)。 渡辺 私、忖度されてますか(笑)。 髙橋 とか言いながら「泳げないのに離婚するのはどうなんだろう」とは思いました。なぜなら、泳げない人は離婚しませんから。 ——なんですか、それ。 髙橋 われわれは今、陸上で生活してるから、泳げるか泳げないかは関係なく暮らしてるように見えますけど、実はひと皮むけば、本来の行動様式が現われてくる。
——本来の? 髙橋 そう、水中での行動様式。われわれはもともと水生動物ですからね。泳げるか泳げないかでくっきりと分かれてくるんです。泳げない人はしがみつく。私なんかも以前、知らずに水深2メートルのプールに入ってしまったことがありまして。足が着かないから、もうあわててあわてて。壁面の凸凹やら、コースロープやら、手当たり次第にしがみつきました。あの感じです。一事が万事しがみつく感じなんで、離婚しないんです。 一同 (爆笑) 髙橋 泳げる人は、しがみつかなくても泳げるからスイスイ行っちゃう。 ——「あの映画は設定が間違ってる」と言いたいわけですか? 髙橋 というか「泳げないのに、なんで離婚するのかな?」。
石原 ちなみに渡辺さんは泳げないんですよね。 渡辺 はい。だけど、このあいだ離婚しました。 一同 エエ——ッ。 髙橋 離婚されたんですか? 渡辺 籍を抜いただけで一緒に暮らしてますけど。ちなみに妻は泳ぎは得意です。 石原 いろんな仮説が崩れていきますね。 もちろん初耳です ——本筋、辿りつかな過ぎますが、話を進めます。原作にはないけど、映画では主人公は妻と離婚する。子どももかわいそうなことになりますね。 髙橋 ノンフィクションが原作の場合、そこが難しいです。実際に妻は実在するわけですからね。映画化となれば、彼女の許可も必要になる。そこで「はたしてこれでいいですか?」と本人に読んでもらう。彼女は編集者なんで、自分との違いという観点ではなく、女性の描かれ方に着目するわけです。すると、中年の男が離婚して若い美容師と恋に落ちるのはどうかと。 石原 若い女性に流れるのはありがちだと。 髙橋 あと、設定も「男が哲学、女が感性」。この色分けはどうかと。 渡辺「本当に美容師でいいのでしょうか?」とメールをいただきました。 髙橋 実際、私が通う教室は、高橋桂コーチも女性で、生徒も全員女性です。しかもそのひとりは小澤征爾さんの娘さんだったりする。ほかの生徒さんもすごいキャリアを積んでるビジネスウーマンとか、理屈でも太刀打ちできない方々ばかりでした。 石原 そんな方々に「なんで立つの?」と論破される日々。 髙橋 そう。だから女性も男の私以上に哲学的なんです。映画でわかりやすく「男は哲学して、女は感覚でやってます」みたいに色分けするのはどうか。高橋桂コーチも「体に従え」という指導をしていましたけど、その考え方もニーチェみたいですからね。 渡辺 ただ、この作品は主人公の屁理屈が魅力なんです。 石原 もしも、みんなが哲学的に屁理屈を言い始めたら……。 ——主人公の屁理屈が際立たない。 渡辺 そうなんですよ(笑)。 髙橋 妻によると、せめて主人公が恋に落ちる美容師は国立大学を卒業したインテリ。たまたま就職氷河期で、手に職をつけたくて美容師になった、みたいな背景が欲しかったそうです。 石原 細かいですね。それを映像にするのはたいへんですね。
渡辺 表現しませんでした(笑)。やっぱり、私が思うのは屁理屈男と感覚の女性の話で「屁理屈」が「感覚」に論破されるのがおもしろい。それがノンフィクションとフィクションの違いかもしれません。 髙橋 原作の現場では、プールのレッスンが終わり、帰りに出口でレッスンで一緒だった人と会うと、さっきとは全然違う人なんです。プールでは化粧も落とさなきゃいけないし、ゴーグルしてるからみんな同じに見えるけど、ふだんは全然違う、おしゃれな方々です。プールで「なんで立つの!」と怒鳴っていた方が、「ごきげんよう」と微笑んだりする。水中がノンフィクションで陸上がフィクションというんでしょうか。 石原 しかし、あのチームメイトを全員描いてたらきりがないですよね。正直、それはめんどくさいなと思ってたんですか? 渡辺 若干思ったかもしれないですけど(笑)。 髙橋 ただ、映像化されることで「自分はこれを書いたのか」と教えられることはありました。 ——どういうことでしょうか? 髙橋 たとえば、ウンディーネをご存じですか。 石原 ごめんなさい。 髙橋 ウンディーネはドイツとかヨーロッパの水の精です。映画を観ていて「高橋コーチはウンディーネだったのか」と気づかされました。 ——と言われても……。 髙橋 水の精、ウンディーネには魂がないんです。だけど、男性に愛されると魂が生まれる。でも、男が彼女をなじったりすると水に帰っちゃうんです。 石原 デリケートな女性なんですね。 髙橋 しかも男が彼女を捨てると、男は殺される。 石原 ただのこわい女ですね。 髙橋 アンデルセンの人魚姫と同じです。高橋コーチはウンディーネっぽい。来てる生徒もみんなウンディーネなんです。 石原 あのおばさまたちも? 髙橋 みんな、ウンディーネ。その中に私が入っていって「なんで立つの?」と言われるんです。 石原 じゃあ逆らえない。 髙橋 最終的には殺されるわけです。 ——実は髙橋さんの大好きなシチュエーション。 髙橋 エッ⁉ 大好きというか、愛の物語です。最近映画化された『水を抱く女』(原題はそのまま『UNDINE[ウンディーネ]』)という作品があるんですけど、主人公がウンディーネ。妻がすすめてくれた映画なんですが、これは名作です。最初は男女の別れのシーン。男が「もう別れたい」って言う。するとウンディーネが「愛してるって言って」。でも男は彼女と別れたいから、口にできない。するとウンディーネが「お願いだから愛してるって言って。言ってくれないと殺すことになるから」。 渡辺 それがオープニングですか。 髙橋 しびれるでしょ? 原作のウンディーネを知らないと、何を言ってるのかわけがわからないシーンです(笑)。 ——すみません。いま、ウンディーネいりますか? 髙橋 泳がないと殺される感じ。私はウンディーネに泳ぎを教わっている。ちなみに妻もウンディーネです。旧姓も「水上」というくらいですから。 石原 では渡辺さんもウンディーネのことは……。 渡辺 初耳です。 一同 (笑) ——……。ということで第2回はここまでです。では、また次回、ふう。いよいよ本題に入ります。入りたいです。 第3回 お金に困ってて…… ——話がおおいに盛り上がるわりには本筋に1ミリも触れてないような気がしてきました。石原さん、なんか当意即妙な質問をお願いします。 石原 合点です。髙橋さんは映像化に関しては「ご自由にどうぞ」というスタンスですか? 髙橋 原作はあくまで素材。渡辺さんにふくらませていただければと思ってました。 石原 渡辺さんは、脚本化するとき、ある程度忠実にという気持ちはあるんですか? 渡辺 もちろんです。逆に忠実にするために、どこをどうふくらませるかに気をつけます。『はい、泳げません』は、まずルポライターの設定が変わる。「なぜこの人がプールに来るのか?」を考えると、その背景に動機が必要になる。 石原 プールに行くしかない状況をどうつくるかですね。
渡辺 私だったらたとえば「身内が亡くなって、自分の無力感を回復するため」とかそういう考え方をします。 ——無理やり編集者にプールに行かされた主人公はありえない。 髙橋 さすがにそれは私も書いていません。 渡辺 つまり髙橋さんは動機を書いてない。 髙橋 この本に欠けていたのは動機なんですね。そうか、売れるには動機が必要なんだ。確かにサスペンスなんかも犯人の動機が重要ですもんね。動機がないからヒットしないのか……。 ——動機はあったんですよね? 髙橋 ありましたけど書いてはいません。「お金に困ってて、行かざるをえなかった」とか、そういうことは書いてない。 一同 (爆笑) 髙橋 でも「あれ? 私はなんでプールにいるのかな」と疑問を抱くという話は書きました。なにしろ水恐怖症なものですから、水中では軽く記憶が飛ぶんです。 石原 読んで、主人公はやむにやまれぬ事情があったんだろうなとは思いました。 髙橋 プールに来る理由は、言ってみれば余白です。原作は全体的に余白が多いんです。妻がどういう人か、高橋桂コーチがどこの生まれで、なんでコーチになったかもあんまり書いてない。レッスンに来る人がどういう職業かもいっさい書いてない。 石原 そのぶん、水の中の描写が濃密でした。 髙橋 映像作品では渡辺さんがその余白部分を映画にされているといえます。 渡辺 たしかに余白を埋めなきゃいけないから、いろいろ考えました。 石原 マニアックな読者がいたら、映画を見て「原作と全然違う」と思うでしょうね。 渡辺 そういう人もいるでしょうね。ただ、そういう人もいていいと思います。みんながおんなじ考えになるのは気持ち悪いんでね。 石原 そうか。つくり手がものわかりよくなることもないわけですね。 いや、おまえじゃない 石原 鼎談も山場を迎えてきました。いい感じですね。 ——そうでしょうか。 石原 では、渡辺さんに脚本ができるまでの話をうかがいましょう。 ——もう終盤なのに、いまさらすぎる質問(泣)……。 渡辺 脚本は、余裕があったらまず書いてみます。あるいはプロットにしてどれぐらいの長さでできるかなとか。『はい、泳げません』も映画にしては長い。全部書こうと思うと2時間じゃ収まらないんですよ。もっとおもしろいエピソードがあるんだけど、連ドラで10話ぐらいにしたらちょうどいい感じなんです。だから、どこを詰めたらいいかと、まずプロットにします。 石原『舟を編む』の脚本のときは、どういうつくり方だったんですか? 渡辺 あのときはプロデューサーから仕事をもらって、小説の『舟を編む』が出たばっかりで、出版社に映画化の話が殺到してたらしいんです。それをリトル・モアの孫さんから「本を読んで書いてもらえないか」「それ、監督は私ですか?」つったら、「いや、おまえじゃない」と言われました(笑)。 石原 そのときの「ちょっと書いてみて」は実現するかどうかはまだわからなかったんですか? 渡辺 東宝だ、松竹だ、東映だと殺到して、そのときに企画書で、候補ですけど主演は誰でキャストはこんな感じでスタッフはこんな感じという企画書を出さなきゃいけない。その中でリトル・モアは弱小だったけど、作者の三浦しをんさんから指名を受けました。 石原 この脚本がいいと。 渡辺 だからスポンサーは集めやすかったみたいで。書いた翌月に撮影に入る感じでした。 髙橋 私のときとは違いますね……。ベストセラー作家との違いですね。 渡辺 毎回脚本を送っていたので、三浦さんからもいろんなメールがきました。ただ、すべて出版社、プロデューサー経由。 ——たいへんそう。 渡辺 読ませてもらって、参考できるところは参考にして「ちょっと譲れない」ところは、直接やれば早いけど、あいだに入ってる人間を介してやりました。 ——ややこしそう。 渡辺 そんなことばかりです。たとえば俳優に脚本を送ると「俳優が違うと言っている」とマネージャーやプロデューサーを通して私のところに来るけど、何が違うのかがわからない。 石原 違うだけしかわからない。 渡辺 だから直して送っても、また「違う」と来る。衣装合わせでその俳優と初めて顔を合わせたときに「こういうことなんですけど」「あ、そうだったんですか」。 ——不毛な伝言ゲーム。 石原 脚本書くよりメール書いてるほうがたいへんですね。でも、原作者は「なんでわかってくれないんだ」みたいなのが、脚本家にあったりするかもしれないですね。 髙橋 私たちの場合は、こちらの意見は基本的に全部渡辺さんに伝えて、「あとは現場で」という段取りでした。きちんとご返答をいただいていたので、伝わってる感じはありました。やはり原作者と脚本家はいったんは顔を合わせて、随時やりとりを続けることが大事なんじゃないでしょうか。顔を合わせておけば、お互いにあれこれ思い悩んでる姿も想像できますからね。 石原 渡辺さんをはじめ、みなさん髙橋さんの作品をいろいろと考えてくださっているんですね。 髙橋 本当にそう思います。私は原作者ですが、書いたことは理解してませんからね。 ——と言いますと? 髙橋 この本がなんの本なのか、自分ではわからない。本人はただ書いただけですから。 渡辺 わかります。 ——わかりません。 髙橋 でも私の場合、妻がわかっている。 石原 奥様は編集者もやってらっしゃるから、客観的な立場から話せるんですね。 髙橋 出版社の人にも「こういう本ですから」と妻が言ってくれます。アマゾンの宣伝、こういうふうにしましょうとか。 ——すばらしい。 髙橋 このたびの脚本でも、妻の指摘を聞いているうちに、「そういう本だったの? これ」と思ったりします。高橋コーチ役を演じる綾瀬はるかさんを観て、こういうことだったのか、と思ったり。 石原 コーチが、映画の役を見て「私がやってるのはこういうことなんだ」ということですか? 髙橋 コーチがどう思ってるのかわからないですけど、映画を通じて、私のほうが「高橋桂コーチはこういう人なんだ」と教えてもらった気がします。綾瀬さんが水の中で仰向けで浮かんでる姿を目にすると、高橋桂コーチもきっとこうなんだろうなと思ったりして。衆生を救う弥勒菩薩みたいだったでしょう。 ——それを本に書いたのではないんですか? 髙橋 みなさんのおかげで作者の意図がわかった、みたいな。そこがノンフィクションの醍醐味ですね。だって原作は、よくわからんでプールに行きました。それでむちゃくちゃなことを言われて、いや、これ困りましたねって書いてあるだけだから。 一同 (笑) 石原 ところで、その後、高橋桂コーチとの交流はあるんですか? 髙橋 ありますよ、メールでやりとりしてます。「まだ来ないのか」って。 渡辺 まだ言われてるんですか? 石原 もう20年以上経ってます。 髙橋 もうずいぶん行ってないです。行きたくないんです(笑)。 ——泳げるんだから、行けばいいんじゃないですか。 髙橋 そういう問題じゃないんです。だから、この本もそうなんですけど、実は私は泳げないんじゃなくて、泳ぎたくないということなんです。 一同 (爆笑) 髙橋 そういうことに気がつくという話ですから。 石原 映画の主人公のイメージとだいぶ違う(笑)。 髙橋 申し訳ありません。 トム・クルーズのファンです ——では、そろそろまとめに入りましょう。まとまるものは何もないと思いますが。 渡辺 映画は、プロデューサーが「金、金」と言いすぎるんです。とにかく儲けようって。それだけじゃないだろうって思いますけどね。 石原 それがいろんなところに軋みを生んでるんですね。 髙橋 原作に高校時代の友人が出てくるんです。大学の先生やってるやつで、彼も泳げないんだけど、「泳げないほうが死顔がきれいだ」って言う。泳げる人は水飲んで溺死するけど、泳げない人は心臓が止まるだけだから死に顔がきれい。だから泳げないほうがいい、とか言ってまして、それを本に書かせてもらいました。 石原 映画にもありました。 髙橋 本人に「映画化された。セリフも出てくる」と伝えたら「わかった! 絶対観に行く!」と喜んでくれて。そのあと「見てくれた?」って聞いたら、「映画館に行ったら、『トップガン』やっててさ」と。 一同 (笑) 髙橋 「『トップガン マーヴェリック』やってて、そっち観て帰ってきちゃった」と。まあ、わざわざ観に行くには行ってくれたことは確かなんで、怒るに怒れず……。 石原 長年のつき合いも『トップガン』に負けちゃった。 髙橋 そのことを担当編集者のイマイズミさんにぼやいたら、「僕、トム・クルーズのファンです」と。「もちろん観ましたよ。やっぱりいいですよ、トム・クルーズ」とか言われて。 一同 (笑) 渡辺『トップガン』と同じ週に初日だったから、絶対見ませんでした(笑)。 石原 プールよりも空飛んでるほうがいいんですね。 髙橋 でも戦闘機ですよ。戦争はもう止めていただきたい。 渡辺 くやしいな。それじゃあ今度は飛行機ものでお願いします(笑)。 石原「はい、飛べません」。 髙橋 宣伝と言えば、私は町内会の運動会で『はい、泳げません』のロゴの入ったTシャツを着ました。誰かに「なんですか、そのTシャツ?」と訊かれるのを待っていたんですが、誰にも訊かれなくて。字がよく見えるように、両隅をつまんでパタパタとPRしたんですが、「本当に暑いですよね」と同情されたりして。 一同 (笑) 髙橋 どうしたら認知してもらえるかが大きなテーマですよね。本もそうですけど。 渡辺 とはいっても、この規模の映画だと製作費より宣伝費のほうが多いんです。 一同 エエ——ッ。 渡辺 製作費は微々たるものなんです。1億ちょっととか、それでも多いんですけど、宣伝費は2億ぐらいあるんですよ。 一同 ……。 石原 本も製作費より宣伝費をたくさん使ってみたらどうでしょうか。 ——考えたこともないし、これからも考えません。 渡辺 それにしても、宣伝費って何に使うのかわかんないです、そんな額。 石原 テレビCMをばんばん流したわけでもないし。 渡辺 不思議なんです。何に使ってるんだろうと思って。
髙橋 いま、インターネットなどでそんなにお金をかけずに宣伝できる時代のはずです。 渡辺 そうなんですよね。できるはずなのに。 石原 本出すと、ネット媒体がいっぱいあって、本文をそのまま使ってただで記事をつくるっていうのが流行ってるんです。 渡辺 同じ記事を違う人が発信してるのもあります。 石原 僕も新しく出た本の抜粋記事を3社ぐらいで出してもらっているんですけど、ほとんどすべてを読んでるに等しい。これ読んだら買わなくていいなという感じです(笑)。もちろん、本の存在を周知してもらえて深く感謝しているというのは、念入りに言っておきたいんですけど。 髙橋 開成高校野球部の『弱くても勝てます』のときは、帯に二宮和也さんの顔写真が掲載されていたので、ファンの方たちが2冊ずつ買ってくれたんです。1冊はきれいにパッキングして保存用。そしてもう1冊を読んでくれるんです。ドラマの放送開始まで待ってられないんですよ。 石原 誰がですか? 髙橋 ファンの方たちが放送開始まで待ちきれないわけです。だから原作を買って、想像をふくらます。 石原 二宮くんがどうなるのかドキドキしながら。 髙橋 そうです。これをやるんだ、あれをやるんだと想像したり、みんなで過去のドラマを振り返りながら反省点を議論したり。そのために原作が必要になってくる。原作は妄想をふくらませるツールなんです。 石原『弱くても勝てます』は売れたんですか? 髙橋 わりと。 石原 でも、妄想ふくらませて読んだファンは、いざ放送始まったら「違うじゃないか」と。 髙橋 そうなんです。「全然違う」と。 渡辺 有村架純が出てくる(笑)。 石原 そんなの原作には出てこなかったじゃないか。 渡辺 旧ジャニーズは本当そうですね。女性アイドルだとそうはいかないんです。男のファンは1回見たらクリアしたみたいな感じになる。でも旧ジャニーズのファンは何回も映画館に行くわけです。 石原 ありがたいですね。 髙橋 それで視聴率が下がると、何がおかしいのか、という話になって、原作がおかしいんじゃないかという話になったりする。原作が合ってないとか、原作がダメなんじゃないかとか。青志先生(ドラマの役名)が青木先生(原作の実名)になってるとか、「原作者の顔がジャニーズ系じゃない」とまで言われましたよ。 石原 濡れ衣じゃないですか。 一同 (爆笑) ——泳げようと泳げまいと、すべての原作は濡れ衣を着せられる。ということで、また次回。みなさん、ごきげんよう。お元気で。
ざっくり、原作と脚本とは?




(*)『弱くても勝てます~青志先生とへっぽこ高校球児の野望~』(日本テレビ系)