本に書かれていないモンテレッジォ(back)
本に書かれていないモンテレッジォ



去年の今頃は、何をしていたのだろう。
遡ってみると、悩んでいた。『本の生まれた村』(『モンテレッジォ 小さな村の旅する本屋の物語』のHP連載時のタイトル)の連載が始まって、ようやく第2章を出稿したばかり。2月に村の紹介サイトを見つけて連絡し、対応してくれたジャコモとマッシミリアーノの好意のおかげで現地を訪問できたものの、手持ちの材料がない。日本に帰る前に、言ったからには実行しなくては、と猪突猛進で出かけてみたものの、村は文字通り空だった。あらかじめ念を押されてはいたものの、いっしょにいった人たちと私、村の入り口で会った熊のようなグリエルモ、数名の村人にバールでおいしいピッツァを作って出してくれたティツィアーノしかいない。人がいないので、暮らしの動線がない。
〈これは、書きようがないかも〉
おいしいご飯をいっしょに食べて、楽しく日曜日を過ごしました。おしまい。
日記なら、そう書くところだろう。
どこかに行っても、メモはほとんど取らない。写真をポストイット代わりに使っている。ときおり数字はメモすることもあるけれど、重要な数字なら後でも調べられるものだ。初めての場所でも、行く前にあまり資料をあたったりしない。人に会うときは、失敬のない程度に可能なら著作などを読んでおくこともあるけれど、たいていは待ち合わせの住所だけを手に行く。初めて見聞きするときの印象が肝心で、メモを見なくても心に止めておくことがあればそれが重要、と思うからだ。
そもそもモンテレッジォには資料がなかった。行く前からものになるのかどうかはわからないので、まずは行ってみるのである。風景写真の数枚でも撮り、ヴェネツィアのベルトーニさんに報告できればそれで十分かも。

山の中の石畳だけの無人の村に着いて、ううむ、となった。去年のポストイット写真を見てみると、
〈困惑〉
〈メモのしようがない〉様子がありありだ。
うつむいて歩いていたのだろうか。やたら足元の写真が多い。

初めての場所に行くとき、もしここに自分が家を造るなら、という空想の住まいに目星を付ける。それでモンテレッジォでも、私ならここ、という家の写真を撮っている。廃屋。平屋。ひと間か二間かも。独りなのだから、それで十分。窓は必要。日当たりも良くないと。
周囲の建物は限界集落だというのにきちんと手入れがしてあり、たとえ山奥でも高値に違いない、という印象だったからだ(もちろん買うつもりで探すのです)。
これかしらね、と私が言うと、マッシミリアーノが
「ここもなかなかいいけれど、交渉に手間取るでしょう。何軒かお勧めがありますよ。僕もやっと家を手に入れて、修復が終わったばかり」
あれです、と外から見せてくれた。

イタリアでも日本でも景勝地のホテルでは、〈海が見えるサイド〉〈都会サイド(道に面していて騒々しい)〉など、窓からの借景が謳い文句になっていることが多い。モンテレッジォで不動産紹介業をするのは、セールスポイントが難しそうだ。全方位が山だからである。この村では、何が家選びのポイントになるのだろう。
〈私ならここかしらね〉
と言ってみたのは、同行してくれたジャコモやマッシミリアーノへの社交辞令だったわけだけれど、いつも会う人が二人か三人だけ、というところで暮らすのはさすがに気が引ける。人と会って話していくら、が仕事の私にとって、この村に暮らすと相手は自分自身ということか。向き合う準備ができていない。
表へ出て山に囲まれ、家に入って山に囲まれる。
想像してみて、ああこれは、と思った。

〈島と同じではないの!〉
私は島が好きなのです。
着くのも発つのも、船がなければ難しい。しかしまた着いたら着いたで、閉ざされた空間での暮らしにはさまざまな制約がある。人間関係も難しい。どこにいても人間関係は各様にやっかいなのだけれど、島は閉ざされているので良くも悪くも凝縮され、実に濃厚な味わいになる。
わけあって6年間船上生活をしたことがあり、島との縁は深かった。モンテレッジォを島として考えてみることにした。そうすると暮らし方や考え方もわかりやすいのかもしれない。
〈陸の孤島、とよく言うことだし〉
そう単純なことではない。陸は陸で海は海、ということをだんだんに思い知ることになっていく。
第二回(2018.07.24)
栗の粉を水で捏ねるには、技が必要


「初めての場所に行くとき、何からどのように取材しますか?」
インタビューでよく尋ねられる。マスコミの同業者であっても、出版社や新聞社に所属している社員記者とフリーランスの記者とでは、仕事の仕方が異なる。
フリーランスの記者でも、受注して取材に出る場合と自主的に動くときとでは、さらに異なる組み立てになる。私の場合は、後者。
自営の通信社(写真と記事を日本のマスコミに売っています)なので、ネタの揃えが会社のブランドとなる。ネタは誰にも知られていないものをどこよりも早く掘り出して、記事にして売ることが商売の肝心要だ。有名な事件を後追いする方法もあるけれど、自分がニュースにして世に出せる頃にはすでに旬が終わってしまう。せっかちなので、耳にしたら、後先考えずにまず走る。私は疑り深いところがあり(職業病です)、自分で確かめてみるまでは信じない。
モンテレッジォは、まさにそういう〈聞いた、走った、見た、驚いた、書いた〉の典型的なネタだった。いつもと違ったのは、行く先が古代だったり中世だったり、至近でも第二次世界大戦あたりだったりしたことである。

「これを食べると、気持ちがね、小学校の夏休みに飛ぶんだよ」
目の前の料理は、すみませんが、美しくなかった。手で捏ねたのがあまりに明白な、不揃いの小さな塊は灰色がかった茶色をしている。市販されている乾麺だけでも、常時イタリアには400種余りのパスタがあるとされている。手打ちパスタも入れると、料理好きの数だけの種類があるだろう。
現存するほとんどのパスタを食べてきた、とひそかな自信があったが(あるときマスコミにほとほと嫌気がさしてしまい、ふつりと止めて、それから十数年間イタリアで農業に従事していたことがありました)、これは初めてだった。
栗の粉を水で練り、丸めただけのパスタは寂しい外見だったが、ひと口噛み締めると、どうだろう!?

じわりと甘く、噛むとほんのり塩味がする。ころんとした塊の表面は、塩茹でしたときにやや溶け、とろりと本体に絡まっている。噛み締めれば噛み締めるほど、栗の味が奥の方から滲み出てくる。
周囲に栗の木、口の中に栗の粉。
皿の上に残った、栗ニョッキから溶け出た粉とオイルをパンをちぎって拭った。それだけでも十分に滋味深い味だった。無駄なものを省いた後に残るのは、核心だ。料理もその通り。栗の粉と水と塩だけで作った料理は、相当の自信がないと出せないはず。
モンテレッジォ村の人たちの、この揺るぎない確信は単なる唯我独尊なのか。あるいは、頑固な純朴者なのか。

この一帯にある他の山村には、どんな郷土料理があるのだろう。
肉も魚どころか、野菜すら栗の粉のニョッキには合わされていなかったのに、食べ終えると福々とした気持ちになった。
「ね、幸せになるでしょう? 栗のニョッキ!」
シンプルであればあるほど、どこにでも誰とでもいつでも溶け込めるものだ。記憶に残るのも、凝ったものではなく単純明快なものだろう。
そうか。モンテレッジォ村の人々は栗なのだ。
イガで防御し内に硬く身を潜めるが、いったん殻を破り外面を剥くと、ほっこりと甘い中身が出てくる。
第三回(2018.08.10)
聴く人たち
本にまとまるまで、いくつもの過程がある。自分のやる気や時間、経済的な事情もさることながら、最も重要なのは見聞きしたことを話す相手がいるかどうか、だと思う。それから、私の場合は締め切り。

日本に帰る二日前に行ったモンテレッジォ村は、どう転ぶかわからないままだったが、〈掘ればきっと何か出てくる〉という強い印象が残った。それまで見たことがあった、離島の内陸部や鉄道の通っていない山岳部とまったく異なったのは、道の敷石に至るまでモンテレッジォは丁寧に手入れが行き届き、〈実際には村にいなくても、いる〉という気配が濃厚に感じられた点だった。
現在の住人は32人(うち90代が4人、新生児が2人)なのに、毎日村の入り口にあるバールは開業している。リグリアのある山奥に暮らしたとき、そこは300名くらいの人口だったが、バールはなかった。
「コーヒーなど、家で飲めばいいだろ?」
吝嗇で有名な土地柄そのものの返事に、異郷へ来たことを実感したものだった。
ところが、モンテレッジォのバールはいつも開いている。店主はティツィアーノとサンドロが交互に引き受けている。

店に入るとすぐ右側に小さなカウンターがある。二人も並べばいっぱいだ。カウンターを挟んで、流し台、端にレジと並ぶ。背後には四人掛けのテーブルが⒋、5卓ランダムに配してある。
ところが、店にはいつも客がいる。歩ける人は、時間ができると店に寄る。バールであって、バールでない。そこは居間であり、会議室であり、待合室、遊戯所、荷物預かり所、交番だった。医者も銀行も薬局も学校もない村で、寄り合う場はライフラインも兼ねている。数百年に渡っての付き合いだ。人間関係は濃厚だろうが、難しいこともあるだろう。
プレスの効いたシャツの袖口を、定規で計ったように同幅に折り返し、自家製ピッツァを出してくれたティツィアーノは、私が何か尋ねない限り、自分からはひと言も話さない。いるけれどいない、というこの手のタイプの人は、都会のカウンター向こうに多い。冷たいようで、実はいつも待機している。
〈まるで東京やミラノのショットバーに来たみたい〉
私が思わず言うと、そうですか、という目を一瞬こちらに合わせて、
「私は、ミラノから移住してきた者です」
ティツィアーノが訳ありに短く答えた。初めて会ううえ、これからまたミラノにマッシミリアーノたちと帰る間際である。〈いったいなぜ〉〈いつから〉〈ミラノでは何を?〉と、次々に尋ねてみたかったが堪えた。代わりに、

〈あの、すみませんが、しばらく村に住んでみたいので家探しを手伝ってもらえませんか〉
と言ってみた。バールは、村の情報拠点なのだ。〈求む貸家〉の貼り紙のつもりだった。
おう、と、彼は一瞬驚いたがすぐ、
「わかりました。いくつか心当たりがあります。話してみましょう」
〈それでは、ミラノの話はそのときにまた〉
暇乞いのコーヒーを飲み、ミラノへ発った。
ネタになりそうだが、その在り処がまだ見えてこない。そういう状況で材料について話す相手がいるかどうかで、原稿の運命は決まる。
誰に話そうか。
東京に戻って、ある書店員さんに村のことを話した。『本屋大賞』に関わる人で、モンテレッジォというイタリアの奥地で同じ趣旨の文学賞がある、ということをぜひ知らせたかったからだ。
私から話を聞くとその人は早速、Premio Bancarella(露天商賞)のサイトを見てみたという。
「イタリア語なのでよくわかりませんでした。でも知りたい。ぜひ調べて、書いて!」

高速道路を降りた道角にいたヘミングウエイの顔が浮かぶ。
〈Vai Yoko, vai! (Go Yoko, go!)〉
村のことをちょっと書いてみてもいいですか、とジャコモとマッシミリアーノにメールで打診すると、間髪を入れずにそう返事が来た。
1行だけの返答はエールだ。いや、消えゆく村に何かとっかかりができるかもしれない、という悲願だ。
〈行け!〉を胸に、話を聞いてくれそうな人を思い浮かべてみる。

そして最初に訪ねたのが、方丈社だった。生まれたてで、ノンフィクションを刊行する。
四人で囲むといっぱいになる机について、窓を向いて座る編集者と営業担当者の背を見ながら、訪れてきたばかりのモンテレッジォ村のことを社長と編集者に話し始めた。ほとんど何も知らないというのに。
それでも二人は、「ほう!」とか「へえ!」を話の合間に挟んでは、延々と続く私の報告を丁寧に聞いてくれた。
ネタの表面を掠っただけなので、広く深く説明できない。しかし
話を聞いてもらっているうちに、どの部分をどう調べると話になるのかが見えてくる。心の中でメモする。話を続ける。質問が出る。答えられない。勉強するべき分野が出てくる。心にメモ。聞き役の短い感想から、イタリア屋の自分には明白なことであっても、日本ではあまり認識されていないことがあるのを知る。心の中に留め置く。

二時間余り話しに話して、二人はただひたすら聞いてくれたのだった。
「連載で行きましょう」
本にするために。本を売る人たち、読む人たち、作る人たちに勇気を出してもらうために。
話し終えた私に、社長が言った。
どうしよう。
二人とは嬉々満面で別れたものの、帰路の電車内で俯いた。心に留め置いたメモは膨大でかつ広範囲だった。
〈行け、ヨーコ! 行け!〉
連載が決まった、と報告すると、
あっという間に各地に散らばる村人たちに一斉に転送され、異口同音に返事があった。
取材し終えるのはいつになるのか皆目見当が付かない。ならば、同時進行で書いてみよう。締め切りごとにネタが揃うのかまったくわからなかったけれど、GOなのだ。
東京で待っていてくれる編集者と社長を拠点に、探検へ出発する気分だった。

第四回(2018.09.03)
村のDNA
連載が決まって、喉元に心臓が上がる。五臓六腑がフツフツと音を立てるような感じ。肝を据えて、とはよく言ったものだ。

実際にモンテレッジォ村を訪れるまでは、さまざまな家族の歴史を並列に書き、〈同時進行で読む、あるイタリアの歴史〉という構成にすればよいのではないか、と漠然と考えていた。本を主軸にした、村人たちのサガ。大きなショッピングモールに並ぶ個々のショップの品々をひとつずつ見ていく感じ、か。
ところが実際に行ってみると、もちろん村人たちの話は十人十色で興味深いのだが、今生きている人たちが自慢に思うのは自分たちの父であり祖父であり、祖先だった。自慢に思う理由は、毎年春になると家族のために働き、それがやがて本の行商へと移ったときには、読者と出版社が追加されて、変わらず黙々と働いたことだった。
立身出世した特別なリーダーがいて皆がその後をついていった、ということでもないらしかった。村人はまとまって、代が変わっても迷うことなく本を売り歩き続けた。モンテレッジォ村のDNAと考えようか。『種の起源』を思う。過去にはさまざまな植生があった周囲の山々は、現在は栗が単種で植生している。土壌や気候との相性、運、同種だけで生存していく楽さと難しさを想像する。長い時間の流れの中でみれば、昆虫も植物も牛馬も、そして人間も世界を作る要素のひとつだ。植物は水と太陽に合わせ、微生物や昆虫、動物が生態系を作る。そして人間。世知以前に、この地で生きるということの根源を探れば、モンテレッジォの人たちの骨肉を成すものがわかるのではないか。
直接に会って話せる相手はごく限られている。でもそれだからよりわかりやすいのではないか。会える人こそ、この地のエキスだと思おう。
事件が起こって取材する、という方法ではなく、まるで植物や鉱物、動物、気象の調査員の気持ちになった。環境調査のような、あるいは考古学の遺跡発掘のような。標本採集に行こう。あるときはルーペで微に入り細に入り、またあるときは目を閉じて指先で触れるだけ。六感での第一印象を原稿にしよう。これは、歴史という樹海に分け入っていく探検なのだから。

瞬時の印象をメモするとその言葉で感想が固定してしまうかも、と写真を撮った。子供達と会うかもしれないので、ポラロイドも用意した。今の子達はイタリアでも、昭和っぽいモノに弱い。会って、その場で撮り合い、すぐに写真が出てくる。余白に日付とひと言書き、相手にプレゼントする(渡す前に、ポラロイド写真をデジカメで記録しておくけれど)。するとお互い、撮影したときのことはけっして忘れないものだ。

今なのにもう〈昔〉になってしまった、今日の出会いのことを。
名刺入れに入るサイズなのが取材資料的には、また最高。
「次回、村にいらっしゃるときは、うちでアルバムをぜひご覧ください」

バールの店外に出したテーブルに陣取り、朝から前を通る子供達とポラロイドごっこをしているのを隣席からずっとニコニコと見ていた、セルジォが言った。ジャコモの父。90歳。彼ひとりで、三章分くらいの話が聞けそうだった。モンテレッジォ初心者の私には、ハードルが高過ぎる。
夏の本祭り頃にぜひ!

記念に夫人と並んで写真を撮った。
「私の話もなかなか面白いのよ」
ジャコモの母が、写されながらそう言った。たしかに。同じ歴史でも、男から見た版と女版がある。
第五回(2018.10.01)
ヴェルディが守ったこと
仕事柄、交通手段を見つけて切符を購入したり、宿の手配をするのは日常茶飯のこと。アクセスが良い場所に行くときは、行きの電車だけ手配して後は到着してから探すことが多い

さて、モンテレッジォ。山の奥。車で行くと楽々だが、距離感は実感しにくい。地形も掴めない。大きな農地、高い山々とひと続きの風景のようで、土地ごとにある風土の違いを感じられないままに境を越えてしまう。電車やバスの時刻に拘束されないという利便性と引き換えに、見逃す要素は多い。小さなニュアンスにこそ、書くヒントが隠れていることが多い。行間というか、空気というか。本を担いで北上した村人たちが見た風景を味わうには、自分も同じように歩いてみればいい。

「無理でしょう。ほとんどが獣道になっていますからね」
張り切る私をマッシミリアーノは笑った。村から栗の木々の間を這い登り、道なき道を毎日走ってしている彼は、栗の実の棚卸ができるのではないかと思うくらいに山々の状況を把握している。両親は村に住まなかった。村から北上していく途中にある町に、取次や出版社を興した五人組を先祖に持つマッシミリアーノは、その町ピアチェンツァで生まれて育った。

偶然だが、私も二十数年前にピアチェンツァ郊外の荘園領主の元領地に建つ田舎家に暮らしたことがあった。ミラノから車で一時間もかからないのに、大自然が広がり、イタリアの中でも最も温和で朗らかな気質だとされる人々が暮らす土地だった。地名はあるものの人家は数軒で、広大なピアチェンツァ一帯のこと、マッシミリアーノに言っても知らないだろう、と思っていた。
「もちろん知っていますよ! じゃあ仲間ですね!」
息を吐く間も惜しいように、次々と郷土料理の名前を挙げた。味覚の故郷が同じだと、それだけで大きく安堵する。主義主張まで同じような気がするのが面白い。

「それでもやはり、僕の味蕾はモンテレッジォの素朴な料理です」
マッシミリアーノは、ミラノに出て大学では法学を勉強した。弁護士資格を有する。ミラノの弁護士に多い、論法では常に先手を打ち相手に隙を見せない、あの独特な尖った感じが彼には少しもない。仕事は何を、と問うと、
「〈ヴェルディの家〉で働いています」
言われてびっくりした。難関のミラノ国立大学法学部を出て、競合の多い法曹関係の生え抜きかと想像していたからだ。モンテレッジォの村興しのために民間企業から協賛金を得たり運営したりするのは簡単ではなく、長けた人間力と管理能力が必要なはずだ。ほぼ一人で担っていると聞いて、広告代理店などで働いているかと考えていた。

ヴェルディ?! あの音楽の?
「たまたま募集がある、と聞きましてね」
受けたら、採用された。管財やさまざまな契約の管理を任されている。
〈ヴェルディの家〉は、ミラノにある。
ジュゼッペ・ヴェルディは音楽家としてだけではなく、朗々と雄大な音楽で民心をまとめて、イタリアがひとつの国家となるよう導いた功労者でもある。ピアチェンツァの近くにあるレ・ロンコーレという小さな農村で生まれた。父は農業に従事。ヴェルディの音楽の原点は、この大地を取り巻く自然にある。

イタリアの父、とも呼ばれるヴェルディは、自分の没した後に入る著作権なども含めた遺産で、家族に恵まれなかった音楽関係者のために終焉の住処と病院を建てるよう言い残した。自身が幼子と妻を病気で次々と失い、どん底の悲しみを味わった。音楽に身を捧げて、家庭を築かずに老いる人は多い。ヴェルディは孤り取り残された者の哀しみを、彼らが愛した音楽で労い看送ってやろう、と考えたのかもしれない。それが〈ヴェルディの家〉である。
中庭の緑の影に包まれた屋内へ入ると、二百年前に飛ぶ。板敷きの温かみのあるコンサートホールは、声楽や楽器演奏の練習所や礼拝堂も兼ねている。建物は廊下続きで隠居音楽家たちの個室や大道具を作る部屋、衣装部屋、食堂、談話室、遊戯室と並び、ヴェルディ博物館を階下に控え病棟へと続く。丁寧に手入れのされた中庭があり、花壇向こうに霊廟。ヴェルディと後添えの妻が祀られている。コンサートホールの演奏や歌声は館内を粛々と流れ、中庭に舞い、霊廟へと静かに下りていく。

音楽を愛する人たちの憩いの空間であり、またその思いが墓参りのようにヴェルディにも届く。
ああ、と感じ入る。

豊穣の大地は、イタリアの心意気だ。ヴェルディは自分の生きて得た悲喜こもごもを音楽を通して還元したのだろう。得たものを分かつ。苦しいことも嬉しいことも。
そういう大地をモンテレッジォの人たちは耕し、枯れたらそこへ根を張ろうとし、あるいは自分の足で踏みしめて乗り越え、各地へ行った。より多くの人たちと分けるために。
「ミラノから鈍行を乗り継いで来てみるといいですよ。旧荘園を縦断しますからね」
マッシミリアーノに言われて、ミラノから電車に乗った。帰りの切符も宿も取らずに。
鈍行はよく揺れた。ミラノを出て少し走ると、車窓からの風景は絵を貼ったように変わらない。停車駅ごとに、乗り込んでくる客が連れてくる匂いが少しずつ違った。乗り続ける人は私の他にはなく、乗っては降りてが続く。小物をスーパーマーケットのビニール袋や景品なのだろう、商品名が書かれたナップザックだけを手荷物に、自転車のように電車を使っている。

乗り換えのために降りた駅は、昔から湯治で知られた温泉郷の近くだ。二時間近くある待ち時間に、駅を出て周辺を歩いてみる。
駅舎には、〈温泉バカンス百周年記念〉と題した観光旅行の参加募集のポスターが貼ってある。温泉があるということは火山か。土壌がこれだけ豊かなのは、火山灰土ということもあるのかもしれない。

地震もあるのか、と思いながら、アペニン山脈の古い村がつい最近地震で大きく損壊したことを思い出す。モンテレッジォとは同じ山脈続きだ。深い緑を抱いたまま、イタリアの背骨と呼ばれる山脈が開かれてこなかった背景を改めて思う。
大地から湯が湧く。イタリアでは、治療目的で〈温泉休暇〉という有給が認められている。最長15日間。

そういえば、古代ローマ時代に遡っても、イタリアの人たちは風呂好きなのだったな。ローマ皇帝たちは、海を越えてアフリカやギリシャまで眺めの良い場所に湧く湯の源を探しにいっていた。今は農地となったこの一帯にも、ローマ皇帝に命じられて温泉探しをした者たちがやってきたかもしれない。
馬の高い嘶きと蹄の音が聞こえてくるようだ。
人々の心身を癒し、満たす。
真の滋養を生む大地で働いた、歩いた村の人たちを思う。
第六回(2018.10.15)
小さな町の偉大な文化人
車窓からの眺めは、いろいろな効能を持つ薬だ。見慣れた景色から離れていく時、戻る時、初めての風景、月も無い真っ暗な中。
見るともなく見ていると、焦燥や不安、興奮や緊張が次第に落ち着いてくる。
今回、取材に行く先が飛行機でひとっ飛び、車ですぐ、という場所でなかったことがどれほど幸いしただろう。モンテレッジォに向かう度に、車中で眠り、ぼうっとして、関係のない本を読み、車内の様子を見て、行きがけに買ったパンを食べる。
〈ゆっくり急げ〉
何度も反芻した。
東京で世話になった編集者が、生前よく口にしていたのを思い出す。
時事報道が仕事で、事件や事故、暴露的なスクープの取材ばかりを続けてきた。ニュースを誰より速く知り伝えるために移動や通達手段に時間をかけるなど、もっての他だった。
ところが、モンテレッジォはどうだろう。
「いつでもまたいらっしゃい。私たちはずっとここにいますから」
会った人たちは異口同音に帰り際にそう声をかけてくれた。

その日ミラノ中央駅から出て鈍行に乗り継いで向かった先は、初めての町だった。Villafranca(ヴィッラフランカ)。〈フランクな(自由、自在、解き放たれた)町〉なのか、あるいは古にフランク族が侵攻してきたときにできた町なのか。名詞と形容詞だけを並べた、没個性の地名だ。
自由な町、か。
かつて町が一つの独立国家だった頃、町から町への往来も簡単ではなかった。地名が固有名詞ではないということから、領土と領土の間にある白抜きの圏を想像する。どちらでもないところ。個性がぶつかり合う中、小休止できるような場所。流れる川のような。

電車は山裾を縫って走る。行っても行っても山で、ときどき干上がったマグラ川の石だらけの河原の上を通っていく。いくつもの中州があるほどの広い川幅で日当たりもよいのに、川沿いは空地のままになっている。数年前の山からの鉄砲水でモンテレッジォへの道が断たれていたと聞いたが、この一帯も山崩れが繰り返し起きてきたのかもしれない。電車は行く。とうとうヴィッラフランカに着いた。

電車から降りたのは、私一人だった。プラットフォームに、ジャコモが迎えにきてくれている。横に若い女性が立っている。黒いミニ丈のワンピースから、よく日灼けした足が健やかに伸びている。
「娘です」
挨拶しなさい、と父親にうながされて一歩前に出たものの、白いキャップを目深に被ったまま消え入るような声で、
「チャオ。……コスタンツァです」
とだけ言い、またジャコモの脇へ急いで戻った。大いに照れている。
「もう高校生なのに、引っ込み思案でして……」
すまなそうな謝辞とは裏腹にジャコモは嬉しくてならない様子で、笑いながら叱るふりをしている。

一人娘のコスタンツァは16歳になったばかり。高校で課題研究としてモンテレッジォ村の本の行商人の歴史を選び、論文を書くのだという。
「お邪魔でしょうが、取材に同行させてやっていただけませんか」
白いキャップのツバ下から、大きな黒い瞳で照れながら〈お願いします〉と瞬きしている。
東洋の見知らぬ人が、自分の故郷のことを調べにきている。いったいなぜ。どこが面白いのか。何をどう書くのだろう。誰がどんな本に作るの。読む人がいるかしら。自分の祖先たちの話が日本まで行くなんて……。
私がコスタンツァの立場なら、きっとそのように思っただろう。
駅から車で向かったのは、このトスカーナからリグリア、エミリア・ロマーニャの三州に囲まれた広大な一帯、ルニジャーナ(Lunigiana)地方をよく知る人の家である。前回会ったときに、ここで生まれ育って郷土史に詳しい人に会ってみたい、と私が言ったのを覚えていたジャコモが、「それならば」と名を挙げた人がいた。
ジェルマーノ・カヴァッリさんという。

その現在の代表が、今日これから会う、ジェルマーノ・カヴァッリさんなのである。

ヴィッラフランカは、静かで人のいない町だった。古いけれど大切に住まわれてきた、という印象がある。モンテレッジォと似た雰囲気だった。
「同じ領主でしたからね」
13世紀、ここも荘園貴族マラスピーナ家の領地だったのである。ならばダンテも訪れたのかもしれない。
もちろん、もちろん、とジャコモは嬉しそうに頷いている。

町は壁に囲まれていて、その入り口で老いた男性が出迎えてくれた。真っ白のシャツに合わせたジーンズの腰が高い。優雅な笑顔で手をすっと差し出し、
「ルニジャーナへようこそいらっしゃいました」
カヴァッリさんは両手で私の手を包み込んで、恭しく挨拶した。
町の入り口から入るとすぐに四方を建物で囲まれた広場になっている。カヴァッリさんの家は、その広場の一面を担う建物すべてらしかった。

入り口を入り、階段をたどり、広い居間に案内される。廊下から居間、ちらりと見えた奥の部屋にも、本。本。本。居間の壁一面にあるいくつもの窓はすべて、今いた広場に面している。
「広場は、ルニジャーナの歴史を見てきました」
窓際に置いた天鵞絨張りの一人がけソファにカヴァッリさんは体を沈め、私にその前の椅子を勧めた。

コスタンツァは私のすぐ後ろに座り、ノートを広げている。ジャコモはその隣で小声で、ここがどういう場所で彼がどういう立場の人なのかを娘に一生懸命に説明している。
二時間だったか、あるいはもっとだったかもしれない。
モンテレッジォを含む、ルニジャーナという一帯がどれだけ肥沃な土地だったかについて、空から地から、息も吐かずに説明してくれた。壮大な講談だった。大きく羽を広げた鷹の背に乗って悠々と山間を飛び、ロバに連れられて一歩ずつ坂道を登る気持ちだった。

あるときは石や水は負になり、あるいは幸をもたらすことがあるのもカヴァッリさんの話を聞きながらしみじみと感じた。土地の豊かさは、彼の博識ぶりと高い品性、穏やかな物腰を見るだけで充分にわかった。土地は人なのだ、と改めて思う。
海から陸からのひっきりなしの往来を見て、町の住人達は通行人を見抜く目も作っただろう。行き交いする人々は、貴重な情報と金と商機を持ってくる。
「それを交換したのが、このヴィッラフランカだったのです」
窓いっぱいに広がる広場を見る。

モンテレッジォには険しい山があった。向こうのムラッツォには、川があった。堰き止めて、管理して、通す。ところがヴィッラフランカは、盆地にある。
〈川越え山越えの難所の前に、ここでも存分にお金を落としていってもらいましょう〉
広場で市が立った。ヴィッラフランカは、今で言うタックスフリーのような役目を果たしたのだった。フランカは、〈自由取引〉の意味だったのか。
市が賑わえば、宿屋もできただろう。ホスピタリティーは(もてなし)、ホステル(宿)へと繫がる。そして、ホスピタルへも(病院)。繁盛する市には、外から利益だけではなく弊害も入ってきただろう。恐ろしい疫病。ヴェネツィアがペストで壊滅的な打撃を受けて滅亡寸前にまで衰退したのも、外からひっきりなしに新参者が往来したからだったろう。
そのうちに一帯の〈もてなし〉〈宿〉〈病院〉〈病い〉についても、歴史を調べてみようか。

先走りする私を笑いながらカヴァッリさんは、
「一帯にはペストの歴史について記録がないのです。かろうじてコレラ伝染があったような。しかしそれも、社会を壊滅させてしまうような被害は与えなかったらしい」
なぜです?
「ここで採れるものだけを食べる、という代々の粗食のおかげで、病いを跳ね除ける強い体質を作ったのかもしれませんね」
天井までの本棚からカヴァッリさんは薄い冊子を取り出すと、
「今日の記念に。この地に興味を持ってくださり、本当にどうもありがとうございます」

再び美しい仕草で私に手渡した。
ざらりとした薄い緑色の表紙には、活版印刷で『栗の文化史』とタイトルがあった。著者は、彼、ジェルマーノ・カヴァッリさんなのだった。
第七回(2018.10.29)
山の小学校で起きたこと
1981年。私にとって初めてのイタリアは、ナポリだった。暮らしの難度の高い町だった。世知に長けていないと即座に出し抜かれるような土地柄であるうえ、前年、町に壊滅的な被害をもたらした大地震後という非日常の状況の中、移住したこともあっただろう。しかし困難に感じた理由は、何より私自身にあった。二十歳そこそこだった私は、日本やイタリアという国の違い以前にそもそも世の中のことがよくわかっていなかった。
初めての土地で風習も環境も知らず、知己も当てもない。ナポリの強い方言はもはや他の国の言葉で、日本での大学時代に机上で得た知識など実生活ではほとんど役に立たなかった。
身が竦む思いを最初に解してくれたのは、近所の子供達だった。幼い子の限られた語彙は、直球の言葉だった。痛い、怖い、嬉しい、好き、嫌い。こういうときにはそう言うのか。小さくて弱いけれど、敏速で柔軟。隙をよく知っている。手や目の届かないところまで見ようとしなくても、足元や目の前にも観るべきものがたくさんあった。目線を下から上げていくと、それまでとは違う世界に出会ったりした。

モンテレッジォに通い始めてしばらく経ってから、小学校へ行ってみることにした。ヴェネツィアの離島に暮らしていたときに、市立図書館で幼児向けの読み聞かせに参加する機会があった。幼子と本を入口に、離島が抱えるさまざまな問題や利点を知るきっかけとなり、それはどんな文献や専門家へのインタビューよりも役に立った。読み聞かせで知り合った幼稚園と日本の幼稚園を繋げてみたらどうだろう。

市立図書館の職員達は提案に喜び、日本側でも興味を持ってくれる幼稚園があり、それから子供達のやりとりが始まった。まだ読み書きのできない就学前の子供達なので、好きに絵を描いてもらい送ることになった。頻度もテーマも方法も決めない自由なやりとりは、穏やかで温かな気持ちの交換に繋がった。
〈同じことをモンテレッジォの子供達ともできると楽しいかもしれない〉
村には学校がない。幼稚園や小学校はどこへ通うのか、とジャコモに訊くと、学区の校長を紹介してくれる、とすぐに返事がきた。一帯の山々に点在する小さな町村には学校はなく、その小学校へ集まってくる。多くの家庭がずっとそこで暮らしてきて、これからも変わらず暮らしていく。子供達の周りには、都市部では当たり前の産業も機関も店舗も娯楽施設もない。

幼い子供達に関わる提案というのは、どこでもどんな目的でも、即時には承諾されないことが多い。昨今の時勢柄、当然のことだろう。でもヴェネツィアで経験した本が世界の扉を開くような経験を、ぜひ山の小学校にも体験してもらいたかった。ナポリの頃のように、子供達から簡素で真の言葉で土地のことをいろいろ教えてもらいたかった。渋面をされてもあきらめずに話してみよう、と校長の返事を畏まって待った。

「ぜひ始めましょう。日本の小学校と交流する機会ができれば、どれほど子供達の視野が広がるでしょう!」
面談に同席したフランチェスカは、小学校三年生の担任教師である。校長の承諾を得るとすぐその場で、一年生から五年生まで(イタリアの小学校は五年教育)全生徒の家庭にこの提案を説明する算段を校長と相談しながら決めていった。フランチェスカ先生がまず、嬉しくてたまらないのだった。
東京の目黒区立五本木小学校との接点を得る機会を得て、こちらも校長、副校長から即、「交流しましょう」との快諾を受けた。
「山村には本の行商人がいた、という歴史を大人も子供達もほとんど知りません。それを、日本人が調べて本にしようとしている。何も無い、と思っていた自分たちの住むところにそんなに重要な歴史があったのか、と驚いたのです。皆、『ぜひ知りたい!』と興奮しています。本の行商人についていっしょに調べ、教え、思い通りに絵を描いてもらおうと思います」

フランチェスカ先生から連絡があった。取材仲間、現る!
新学期が始まる九月から、子供達は任意で学校が休みの土曜日の午前中にも通学し、本の行商人についてジャコモから話を聞き、絵を描き始めた。休日を返上して、遠くの山から子供達を送り迎えする保護者達も、教師たちも、小一時間かけて自宅のある海の町から通うジャコモも大変だったろう。三十名余りの子供達が、それぞれ十点以上の絵を描いた。「描きに描いた」という様子だったそうだ。
クリスマスに合わせて東京の小学校へ絵を送ってきた山の小学校の子供達に、ぜひ礼を言いに会いに行きたかった。連載のためにちょうど行商人達の個別の資料にあたっていた頃で、その血を受け継ぐ子供達に会い、彼らのご先祖達の話に会えた嬉しさとありがたさを伝えたかった。しかしながら日本に戻っていた私はどうしてもイタリアに行くことがならず、「それならばテレビ電話で話しましょう」ということになった。

日本とイタリアの時差は、八時間。日本が夜、イタリアが昼。イタリアで子供達が授業を終えて下校する前を見計らって、私はタブレットから電話をかけた。
黒板! フランチェスカ先生。大勢の子供達。全員がカチンコチンに緊張しているのが、タブレット越しにも伝わってくる。一人ずつ自己紹介をしてくれる。誰もふざけない。きちんと立って、一生懸命に名前を言い、何か言おうとしてでも黙り込む。
素晴らしい絵のお礼。ご先祖の話が本になる報告。「そういう村に住んでいるなんて、すごいことです」。

モンテレッジォの近くの山村と日本。お互いに信じられない。真っ暗な窓から日本の夜を見せ、足元の畳の目を見せ、障子に触れて音を聴かせる。
「とても遠いのに、ごくそばにいるみたい」
本は魔法の絨毯です、と電話を切った。
三月に子供達の描いた絵と文章を、校長とジャコモとフランチェスカ先生が力を尽くして本にした。

〈私たちの本とヨーコの本と、いっしょに書店に並ぶ日が来ますように〉
出来上がった本といっしょに小学校からメッセージが届いた。
本を作るということ、本を届けたいと思う気持ちを子供達から教わった。
第八回(2018.11.18)
小さくて大きなライバル

子供を見ていると、人生の復習予習をするような気持ちになる。まだそれほど多くない語彙で、核心を突くことを言う。稚気が真実を当てることは多い。先入観の無い視点は、純粋な価値を見抜く。子供達が読み書きを学んでいくうちに、核心の先が少しずつ丸まって代わりに狙う範囲が広くなる。いいような、悪いような。
モンテレッジォ村には学校がない。近隣の山々の村も同様の状況だ。いくつかの山をまとめて学校区を作り、ひとつの学校へ山々から子供達が集まってくる。一人しかいない村もある。山の奥の一軒家からやってくる子もいる。
山々の代表が一堂に会して、勉強が始まる。イタリアの小学校は、5年間教育だ。六歳で入学して十歳で卒業していく。全員が同じ中学に上がるとは限らない。保護者の都合で、山が変わる子もいる。五年間で得た友達は、一生の土台を作る。幼い子からしっかりした上級生までが、一人として仲間はずれを作らずにまとまっている。
フランチェスカ先生は、美しい人だ。長身で、まっすぐの黒髪をそのまま背に流している。何より、優しいのに厳しい。正しく、真面目で、でも笑上戸で、感激屋だ。
日本の小学校と交流しませんか、と私が提案した途端、目をまん丸に見開いて〈もちろん!〉という顔をした。キラキラしたあの目はけっして忘れないだろう。

同じ目で、子供達の発言を熱心に聞き、嬉しそうに頷いてから、
「まったくその通りですよね! ミケーレ、面白いことに気が付いたのですね!」
感心する。
子供達はいつも、フランチェスカ先生のキラキラする目を見たい。先生は、善いことはどんな小さなことでも見逃さずに褒め、ちょっとこれは、という残念な出来事は厳しく手短に注意をし、すぐご破算にして次へと進む。
連載終了の後いくつかの章を書き下ろし写真原稿も脱稿した直後に、私は山の小学校を訪れた。日本からテレビ電話で話をしたきり、子供達とはまだ直接に会ったことがなかった。

三月なのに、数日前から霙が降りやまない。仕事を休んだジャコモが、小学校の近くの山麓へ迎えに来てくれた。バール兼エノテカ前で待ち合わせた。夏が終わると近隣にあるいくつかの宿は、すべて閉まってしまう。モンテレッジォ村の人達が留守宅を使ってくれていいから、と声をかけてくれたが丁寧に辞退した。ジャコモが、「山は冷え込みが厳しいので、この霙模様では二日ほど前から暖めておかないと凍りますよ」と、教えてくれたからだった。
夏でもないし独りなので、テントを張って野宿するわけにもいかない。そういうときはどうするか。
近くに食堂か酒店はないですか、とジャコモに尋ねた。簡単に宿が見つからない場所でも、バールか食堂の一軒はあるものだ。僻地で飲み食いして、運転できなくなる客がいる。おしのびであえて人里離れたところで食事をし、そのまま週末の夜を過ごす二人連れもいる。勘定を払い、「今晩、貸してもらえる部屋はありますか」で、鍵を受け取る。私が泊まったのも、そういう店だった。

昨年の暮れに日本からのテレビ電話でヴァーチャル訪問したあの学校が、子供達が、先生がリアルにそこにいる。
山の学校だし、限界集落の子供達が集まるような環境だ。古くて小さな平屋の建物を想像していたが、来てみるとガラス張りの斬新な正面玄関に迎えられた。吹き抜けの玄関口は広々と明るく掃除が行き届き、天井までの高い壁一面に無数の絵が展示されている。
ジャコモといっしょに教室に入ると、46のキラキラした目がいっせいにこちらを向いて、
「ブォンジョルノ!」
あ、ヨーコだヨーコだ、ニッポンだ、チャオ、ワオ、やったー、ようこそ!
ピイチクと小鳥がさえずるように、呟きが広がる。
こんにちは、と挨拶し終わらないうちに、あちこちで「はい!」「はい!」「はい!」と、手が挙がる。誰よりも高く上げようとして、腰を浮かす男の子もいる。
くりくりと目を動かしながら、女の子が教壇まで走り出てきて花束をくれる。

「今朝、うちの庭に咲いた花です」
椿と冬バラ。棘が丁寧に除いてある。三、四本の花は、女の子の手のうちに入るくらいの長さに切ってある。そうっと二本指で摘み上げるようにして、小さな花束を受け取った。じいっと私の手元を見ている女の子。せっかくだから、胸に付けましょう。
「皆、今日をどれほど楽しみに待っていたか!」
フランチェスカ先生が次々と生徒を当てていく。皆、初めて見るニッポン人に訊いてみたいことが山ほどあるのだ。

「日本では椅子には座らないのですか。どうやって座るのですか」
私は急いで、机と机の間に正座して見せる。
わあ。
「足は痛くならないの?」
「何が好きですか」
「東京ってどんな町ですか」
「僕は小説家になりたいです。どうしたらいいの?」

一時間ずっと質問に答えても、まだ足りない。先ほどから手がこそばい。ふと見ると、私が卓上についた左手の甲を、最前列よりさらに前に出てきた子が机の下から精一杯に手を伸ばして小さな人指し指でずっとトントントントンと突いているのだった。机の下に入ってしまうくらいの小さな男の子は、前髪を一直線に切り揃え耳の上をきれいに剃り上げている。
はい、では君。どうしたの? 何が訊きたいのですか?
「1386年に日本ではどういう服を着ていましたか」
大きな声で一気に言った。
レオ君。まだ学校には上がっていないけれど、「日本からヨーコが来る」のだから、兄達に手を引かれて特別に登校したのだという。ずっと自分に順番が回ってくるのを待っていて、やっと質問できてあまりに嬉しくて目が潤んでいる。

なぜ具体的な年を出して、質問するのだろうか。
レオは、兄達がこの数ヶ月、土曜日も学校に通って一心不乱に絵を書いたり、父母の古着を着てお芝居の練習をするのを見てきた。「ずっと昔の山の村で起きたことを、皆で調べて絵に書いてまとめているんだよ」と、兄達から聞いた。絵に描く子供達もいれば、その話を劇にして演じる子達もいるらしい。
レオは羨ましくてしょうがない。まだ読み書きができないので、いっしょうけんめい兄達やその級友達が話すのを聞いている。
自分達が住む山の村から、本を籠に入れて遠くの町まで届けにいった行商人達がいたという。
「おじいちゃんのまたおじいちゃん、そのおばちゃんやおじちゃんの話なんだから」
行ったことのない外国の町の話、イタリアの遠くの町での出来事、本屋になった村人達。

本を書く人が、山の村の本の行商人達のことも書き、小学校に来るという。
レオは、村のことが自慢でならない。
「ではヨーコ、1832年の日本ではどういうものを食べていましたか?」
年号は、村の足跡だ。村の足跡を辿ると、今の自分達の暮らしがある。
皆が描いた絵の中に、フランチェスカ先生はまだ学校には来ていないけれど、レオの絵も入れた。

出来上がった絵を抱えて、ジャコモはあちこちの出版社に声をかけた。そして一冊の本になったのである。その話を聞きつけて、地元の新聞がジャコモをインタビューして記事にした。その記事を読んだ南部イタリアの港町が、「ぜひ名誉招待客として参加を」と、夏の本の祭典『古い町の本』(http://www.librinelborgoantico.it/)に招待した。
突然の朗報に、山は湧いた。
行ける子、行けない子。
大きなバスを借りて、山から南部へ夜通し走っての参加となった。電車の通っていない山から海へ。行く途中に、けっして一人では簡単に行けない南部内陸の町も通っていった。バスは魔法の絨毯だ。

そして、本の祭典へ。美しい港町の夏の夜、舞台に上がった子供達を市長が歓待して、子供達が創った本を賞賛した。
家族の歴史が世界につながる。
誇らしい思いは、一冊の本が子供達とその家族に贈った宝物である。
そしてその宝物が、『国際文学テザウルス・コンクール』の〈未来への才能〉部門(https://www.concorsiletterari.net/bandi/premio-internazionale-di-arti-letterarie-thesaurus-la-brunella-vii-edizione-2018/)

でなんと、最優秀賞を受賞することになったのである(2018年11月18日授賞式)。
山の小学校の皆さん、おめでとうございます。
すごいね! よかったね!
協力:
Ringraziamenti a:
Scuola Primaria “Livio Galanti” di Apriola
Associazione Grande Maesta’ di Montereggio
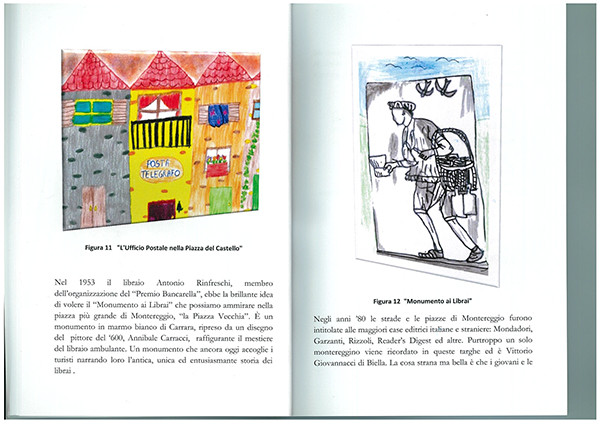
Preside:prof.Maria Grazia Ricci
Maestra Luciani Francesca per “Il Libro nella Gerla. Storia di Montereggio Paese dei Librai”
Maestra Rosa Monica per il laboratorio teatrale “I Sentieri dei Libri”

Antoniotti Emanuele, Baldassarre Michele, Barbieri Gaia, Bazzali Lorenzo, Bertolini Costanza, Beyan Daniel, Biasini Emma, Bielli Sofia, Di Gregorio Lorenzo, Ferdani Alex, Filippi Emanuele, Giorcelli Alice, Hoxa Meme, Nadotti Edoardo, Peccia Mariastella, Piastri Luca, Scognamiglio Andrea, Scognamiglio Leonardo, Terranova Andrea, Tommasini Giada, Tommasini Massimo, Tonelli Rebecca, Xhuveli Isabel
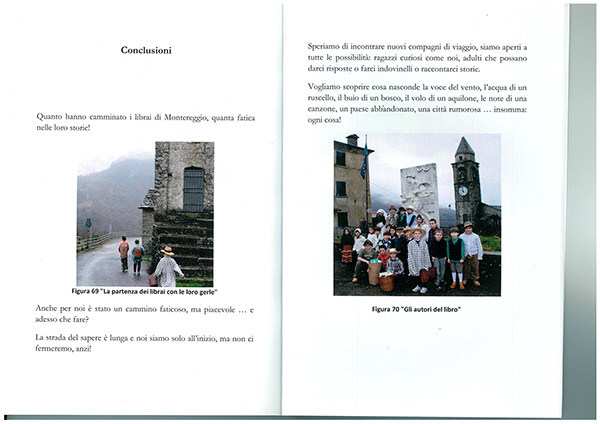
Bertongni Filippo, Bernardini Emma, Vignudo Nicole, Lucchetti Joel, Chippour Samir, Corrado Enrico, Navari Francesco, Husar Gabriel, Sanna Michela, Tonarelli Lara, Pedinotti Damiano, Galleri Tommaso, Tonelli Beatrice, Mariani Eugenio, Crispino Benedetta, Romano Iris, Calani Letizia, Bernocchi Erika, Azzolini Nicola, Magurno Nicolas, Barbieri Celeste, Piola Serena, Fabiani Tina
Maucci G., Il Libro nella Gerla. Storia di Montereggio Paese dei Librai, Montereggio, Associazione di Maesta’ di Montereggio, 2018
第九回(2018.12.08)
足るを知る

本当に栗ばかりなのだった。山の色が変わり、栗が降る。
村の人に案内してもらい、山道を歩いた。ところどころに小屋の跡のようなものがある。四本の柱がかろうじて残り、屋根が朽ちてぶら下がっている。
「ここに栗や払った枝を集めて、干したり蒸し焼きにしたりしたのです」
イガから外し皮を剥き、実を取り出す。実はすり潰して粉にする。周囲すべてが栗だけが植生する山なのだから、山麓に機械化した加工工場があってもよさそうだったが、ない。製粉の原材料として栗の実を出荷する大型の集積所もないのだった。

自分たちの使う分だけ山から貰う。必要以上の栗を取り、商売にして儲けようとしない。手の届かないところで落ちた実は、動物の餌になったり土に戻ってモンテレッジォの滋養となる。自分たちでできる範囲で暮らす。足るを知る。
初めて村を訪れると、「こんなに質素なところで、どう暮らすのか。もの足りなくないのか」と不安に思う。ところが何度か通ううちに、あるいは少し暮らしてみると、充足する、ということの本来の意味を実感する。
村人達は、学校もなく病院もなく店もなく銀行もなく、足りないことだらけの生活を送っている。

「なくても困らないように、それぞれ工夫するようになりますから」
バールで隣り合わせた女性が言う。バスが通っていなくて不便だが、送り迎えのための時間は一日の流れにメリハリが付く。気候の良い時期には、父親とオートバイで通学する女子高校生のアレッシア。父親の背中にしっかり掴まって、山を下っていく。話はできなくても、大切な父娘の会話のひと時だ。
週に二回、小型冷蔵トラックが村の広場にやってくる。箱型の荷台の扉を開けると、小さな商店に早変わりだ。野菜から卵、肉魚、パン、乾物、乳製品、缶詰にはじまり、日用品も売る。運転席から車内に移り乗った店主が、一人で肉を切り分け、魚を包み、野菜を量って、衣服を

広場の陽溜まりにミニトラックが店開きをすると、あちこちから人々が三々五々現れる。杖の老人に手を添える子供達。さかんに尻尾を振ってトラックの下で待つ犬。立ち話。次回への注文を告げる人。店主が積んできた何足かの運動靴を試す人。車内には数センチの隙間もない。すべてが何かの商品棚になっている。同乗して山々を回ってみたい。
店主は気持ち良さそうに物を売っている。手際良く商売が成り立つ

と思い出す。
村人達は店主の手元と目を見ながら、自分の番が来たら間髪を入れずに声を上手にかけて、あれこれと注文したり尋ねたりしている。
広場の一角に、露天商の学校を見る思いだった。
これ以上の何が必要だろう。


 で小学校と繋がって、一人一人と話したのを思い出します。気を付け、の姿勢で立ち自己紹介をして、どの子もきれいな格好をしていた。
で小学校と繋がって、一人一人と話したのを思い出します。気を付け、の姿勢で立ち自己紹介をして、どの子もきれいな格好をしていた。